春のゆらぎに負けない!質の良い睡眠をとる為の9つの大事な事

3月に入り、日中は暖かさを感じる日も増えてきましたが、まだまだ朝晩は冷え込み、寒暖差が激しい日が続きます。
また、卒業、入学、就職、転勤にともなう引越しなど・・
生活環境が大きく変わる人も多いのではないでしょうか。
このような3月の時期的な特性は、私たちの自律神経に大きな影響を与えます。
寒暖差や気圧の変化、環境の変化によるストレスなどで、自律神経が乱れやすくなり、心身に様々な不調が現れることがあります。
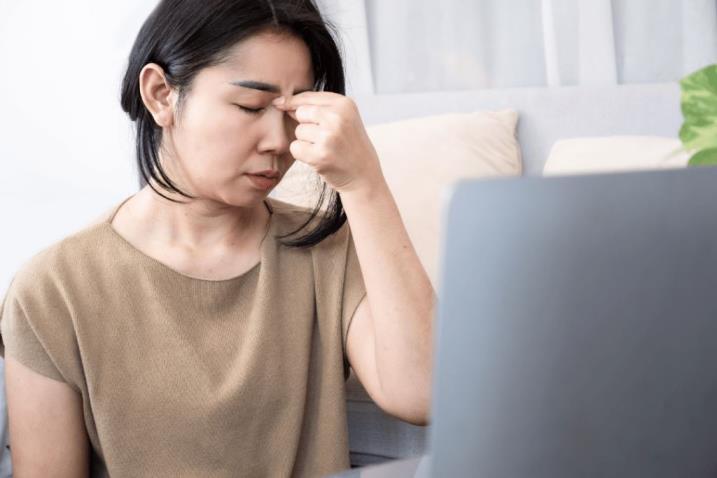
自律神経の乱れには様々な症状がありますが・・・
昨今、お悩みの深いのが睡眠の問題です。
そこで今回紹介したいのが、自律神経を整え心身ともに健やかに過ごす為に最も重要な睡眠の質を向上する為の9つの大事な事をお伝えします。
はじめに

睡眠は、自律神経を回復させ、ホルモンバランスを整えるために非常に重要です。
特に入眠直後の深いノンレム睡眠(徐波睡眠)時に、成長ホルモンが分泌して心身の疲労を回復に導いてくれます。
この、ノンレム睡眠を深くする為には、日中や平素の習慣がとても重要になります。
以下、ノンレム睡眠を深くする為に重要な9つの事を紹介します
1 メラトニンリズムを味方にしよう
視神経から強い光が入ると松果体(しょうかたい)という脳の中央にある部位を刺激して、メラトニン(睡眠を促す脳内物質)代謝のリズムを整えて、ノンレム睡眠を深く出来ます。
視神経からの光刺激から15時間後にメラトニンが分泌し始めて眠たくなると言われています。
ですから、朝7時に日の光を浴びる人は10時には眠たくなるわけです。
そして、12時前の睡眠がノンレム睡眠を深くして成長ホルモン分泌も活発化すると言われています。
つまり、朝日をしっかり浴びて早めに眠れば深い睡眠が得られるということです。
2 体温リズムを整えよう

人の体温は昼間高く夜低いのが普通です。
夜間の体温は昼間より0.5度から1度程度低いといわれています。
そして、深部体温が表皮体温よりも2度程度低い時に質の良い睡眠が得られる事が分かっています。
この体温リズムを上手に整えるのにお勧めなのが入浴です。
寝る1時間〜1時間半前に、ぬるめのお風呂(38~40℃)に15~20分程度浸かるり、からだ全体を温めた後に、からだはしっかりと保温を保ちつつ手足を解放(保温靴下などで温めない)すると、表皮体温が高く深部体温が低い状態が出来ます。
体温リズムを整えて深い眠りを促しましょう。
3 夕食は消化してから寝よう
食事量及び食事の内容によりますが、食べたものが消化するのに最低3時間は必要とします。
内臓が働いている状態だとノンレム睡眠が浅く、疲労が回復しません。
夕食は早めに少なめにすませて、食後3時間以上空けてから眠るようにしましょう。
4 カフェインを控えよう
カフェインはアドレナリンとともにコルチゾール(副腎で作られる代謝を促すホルモン)の代謝を促します。
コルチゾールの血中半減期は1時間半程度、ほぼ消滅にかかる時間は7時間程度です。
コルチゾールとメラトニン(睡眠を促すホルモン)は逆相関関係にある為、コーヒーを飲んで7時間程度は眠りにくい状態となってしまいます。
出来ればコーヒーは午前中、少なくとも午後3時までにしたいものです。
5 アルコールはほどほどに
アルコールは入眠を促す作用がありますが、それは一時的なものです。
アルコールを代謝する時に発生するアセトアルデヒド(毒性物質)の覚醒作用により深いノンレム睡眠は得られなくなります。
アルコール代謝にかかる時間は体質により様々ですが、少なくとも酔いを醒ましてから眠りにつかないとノンレム睡眠は得られません。
6 ストレスを避けよう
一瞬の興奮は自律神経系のストレス反応によりアドレナリンが放出されます。
血中アドレナリンは比較的早く半減(15分程度)し、1時間程度でほぼ消滅します。
しかし、ストレスが持続するとホルモン系のストレス反応(HPA軸反応と言います)が起こり、コルチゾールが代謝されます。
カフェインを取った時と同様に、血中コルチゾールレベルが高いとメラトニンが代謝されないので、眠れなくなってしまいます。
ですから・・ストレスをなるべく避けないと深い睡眠・質の良い睡眠が得られなくなってしまいます。
また、睡眠前及び睡眠中の電磁デバイス(スマホなど)もストレス源になります。
ブルーライトがメラトニン代謝を妨げるだけではなく、睡眠中のスマホの電磁波にも気をつけたいものです。
7 運動をしよう

有酸素系の運動は、セロトニン活性を高めます。
日中作られたセロトニンが夜間にメラトニンへ代謝する為、日中の有酸素運動が質の良い睡眠を促してくれます。
筑波大学の研究でも、日中に活発なウォーキングなどの運動を行うことで、深い睡眠が得られる事が明かにされています。
1日30分の散歩でも睡眠の質が改善するといわれています。
また、適度の筋力トレーニングは、睡眠時の20倍の成長ホルモン分泌が期待出来るというデータもあります。
この、成長ホルモンが深い睡眠を促してくれます。
さらに、良質な睡眠をとる為には睡眠圧力が重要といわれています。
睡眠圧力とは日中の肉体疲労が圧力となって入眠が促進されるものです。
つまり、運動による適度の肉体疲労が圧力となって質の良い睡眠を促してくれるわけです。
ただし、強度の高い運動を夜間にすると交感神経が働いて入眠を妨げる場合もあるので注意してください。
8 バランスの良い食事をしよう

良質な睡眠をとる為にはバランスの良い食事が何より大事です。
心がける事は沢山ありますが・・
次の2つは絶対に重要です。
1)血糖値が乱れる様な食事をしない事
血糖値の乱れと睡眠はとてもかかわりが深いのです。
なぜなら、血糖値が乱れて低血糖になるとコルチゾールなどの代謝をあげるホルモンが分泌されてしまうからです。〈カフェインの項〉〈ストレスの項〉で紹介したようにコルチゾールとメラトニンは逆相関関係にあります。
血糖値が乱れる様な食事(糖質過多食)をしている方は、質の良い睡眠をとれなくなってしまう可能性があります。
2)メラトニン代謝を促す栄養素を取る事
睡眠ホルモンであるメラトニンは日中作られるセロトニンが代謝するものです。
ですから、セロトニンの素となるアミノ酸やビタミンB群を朝からしっかり摂ることが重要です。
「朝食抜き、あるいは朝食はパンのみ」みたいな食生活は、日中のセロトニン生産が低調となり睡眠の質も悪くなる可能性を否定できません。
また、セロトニンがメラトニンに代謝する時に重要なのがマグネシウムというミネラルです。
マグネシウムは日中の活動でどんどん消費します。
ですから、継続して補給する必要があります。
「疲れているけど眠れない」というのは、マグネシウム不足によるメラトニン代謝不全かもしれません。
アミノ酸・ビタミンB群・ミネラルをたっぷり含んだ日常食は、卵・大豆製品・ナッツ類・お魚・緑黄色野菜などです。
特に朝食で、夜間に脳および肉体の疲労回復の為に消費した糖質・アミノ酸・ビタミン・ミネラルをしっかりと補給する事が、質のよい睡眠を得る為のメラトニン代謝を促す土台作りとして・・とても大事だと言えます。
9 腸内環境を整えよう
メラトニン代謝を促す栄養をしっかりと摂取していても、腸内環境が悪ければ良質な睡眠は得られません。
なぜなら、メラトニンのもととなるセロトニンの代謝に腸内環境が係っているからです。
つまり、腸内環境が悪いとセロトニン代謝レベルが落ちて睡眠の質が悪化するということです。
腸内環境改善には様々な方策がありますが・・
最も大事なのは、加工食品を食べない事、化学的なもの(農薬・遺伝子組み換え食品・薬・塩素など)を口にしない事です。
加工食品や化学的なものは腸内細菌を減らすとともに腸の栄養吸収膜を痛めます。
加工食品や化学的なものをしっかりと引き算した上で、発酵食品(納豆・味噌・漬物など)や食物繊維(野菜・きのこ・海藻など)を積極的にとることによって、質の良い腸内細菌が育まれ、腸内環境が整います。
昔ながらの自然な食品(和食がお勧め)がお勧めです。
睡眠の質を整える9つの大事な事を紹介しました。
これらのセルフケアを試しても改善が見られない場合は、自律神経調整のプロである「自律神経整体ゆるむ」をご活用ください。
自律神経の不調対応実績延7500件の整体院長「須藤」が、あなたにピッタリな施術で自律神経を丁寧に整えて、自然に眠れる身体に導きます。
ぜひお気軽にご相談ください。

一緒に春を元気に過ごしましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!!
自律神経整体ゆるむ
整体院長 須藤孝志
不眠・睡眠障害でお困りの方は、こちらの記事もご覧になってください。
不眠・睡眠障害の整え方(完全ガイド)
施術体験のご案内
心身が整い眠りやすくなる感覚をあなたのお身体で確かめてください。
ご希望日のご予約をお取りいただける様調整いたします。
予約枠には限りがあります。思い立った今が試しどきです。
施術体験の詳細は下記バナーをクリックして「施術体験」のページをご確認ください

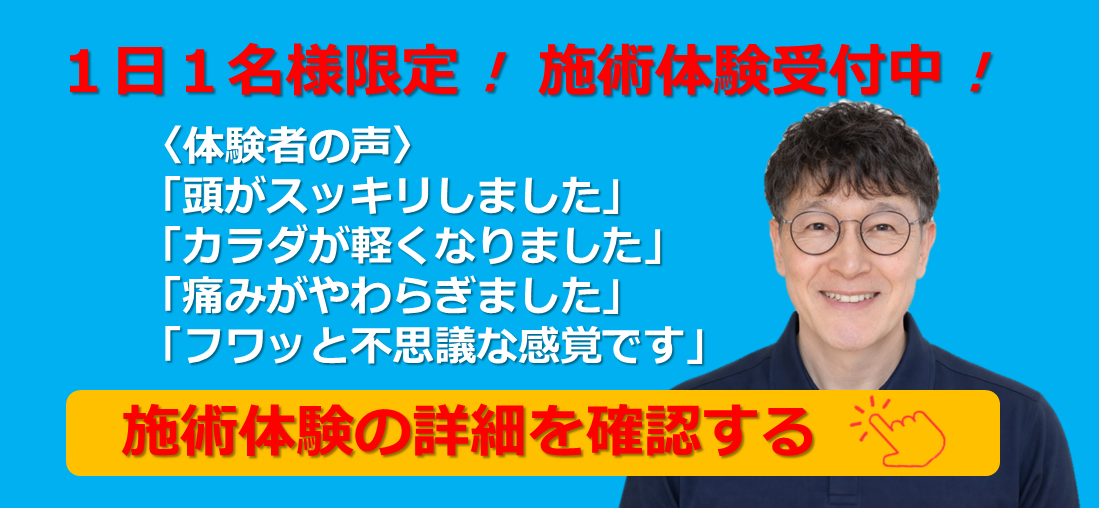
※既存の利用者様のセッション時間確保のため人数に制限を設けさせて頂いております



