まさか!?普段の食事があなたの睡眠の質を下げている?

はじめに
こんにちは、自律神経整体ゆるむ 整体院長の須藤です。
最近こんなこと、ありませんか?
・夜中に何度も目が覚める
・寝ても疲れが取れない
・朝起きた瞬間から体がだるい
これらの症状、実は「食べ物」が関係しているかもしれません。
特に、知らず知らずのうちに摂っている「炎症を促進する食品」が、あなたの自律神経や睡眠の質に深く影響を与えているかもしれません。
炎症と自律神経、そしてホルモンの関係
私たちの体は、ストレス、睡眠不足、食生活の乱れ、化学物質など、さまざまな刺激に対して「炎症」という反応を起こします。
炎症は本来、体を守るための働きですが、これが慢性的に続くと、自律神経に負担がかかり、体調不良の原因になります。
そしてこの「慢性炎症」が続くと、体はそれを抑えるために、コルチゾルという抗炎症ホルモンを持続的に分泌します。
コルチゾルはストレスホルモンでもあり、日中には必要なものですが、夜になっても血中のコルチゾル濃度が高いままだと、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられてしまいます。
メラトニンは、暗くなってくると脳の松果体から分泌され、自然な眠気を引き出してくれる重要なホルモンです。
しかし、コルチゾルが過剰な状態だと、体は「今は眠ってはいけない」と判断し、メラトニンが十分に作られません。
つまり、慢性炎症によるコルチゾルの持続的な分泌が、結果としてメラトニンの妨げになり、睡眠の質を大きく下げてしまうのです。
特に40代後半の女性は、ホルモンバランスの変化も重なるため、自律神経も乱れやすく、この影響を強く受けやすい傾向があります。
炎症を促進する食品とは?
私たちの食生活の中には、炎症を引き起こす食品がたくさんあります。以下のような食品に心当たりはありませんか?
・加工肉(ハム、ベーコン、ソーセージなど)
・トランス脂肪酸(マーガリン、スナック菓子など)
・精製された炭水化物(白パン、うどん、菓子パンなど)
・精製糖(清涼飲料水、ジュース、甘いお菓子など)
・揚げ物やファストフード

これらは体内で慢性炎症を引き起こしやすく、自律神経がポリヴェーガル理論でいうところの防衛モード、すなわち戦闘モード(交感神経優位)もしくはシャットダウンモード(背側迷走神経優位)に傾いたままになってしまいます。
その結果、寝つきが悪くなったり、深く眠れなくなってしまうのです。
睡眠の質を高めるために食生活を見直そう
では、どうすれば睡眠の質を上げられるのか。
ポイントは「炎症を抑える食べ物」を積極的に取り入れることです。
・良質なタンパク質(鶏むね肉、白身魚、卵、大豆製品など)
・抗炎症作用のある野菜や果物(ブロッコリー、トマト、ブルーベリー、アボカドなど)
・オメガ3脂肪酸(サバ、イワシ、亜麻仁油、チアシードなど)
・発酵食品(味噌、納豆、ぬか漬けなど)
・ビタミン・ミネラルが豊富な食品(海藻、ナッツ、雑穀など)

こうした食材を日常的に取り入れることで、体内の炎症が落ち着き、自律神経も整いやすくなります。
「寝ても疲れが取れない」人は、自律神経ケアも必要です
とはいえ、すでに乱れてしまっている自律神経のバランスは、食事だけで整えるのが難しいこともあります。
そんなときは、外側から自律神経にアプローチする方法も必要です。
当整体院「自律神経整体ゆるむ」では、自律神経に直接働きかける整体を行っています。
緊張しすぎた神経や筋膜をやさしくゆるめることで、眠れる体、回復できる体を取り戻すサポートをしています。
「いろいろやっているのに、なぜか眠れない」
「朝から疲れていて、日中ずっとしんどい」
そんな方は、一度自律神経のバランスを見直してみませんか?

今日から始める本質的な健康
あなたの眠りを妨げている原因は、夜ふかしでも年齢でもなく、「食べ物」かもしれません。
本質的な健康は、「生活習慣」と「自律神経の調整」の両方がそろって、はじめて実現します。
ぜひ今日の夕食から、小さな一歩を踏み出してみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
自律神経整体ゆるむ
整体院長 須藤孝志
不眠・睡眠障害でお困りの方は、こちらの記事もご覧になってください。
不眠・睡眠障害の整え方(完全ガイド)
施術体験のご案内
心身が整い眠りやすくなる感覚をあなたのお身体で確かめてください。
ご希望日のご予約をお取りいただける様調整いたします。
予約枠には限りがあります。思い立った今が試しどきです。
施術体験の詳細は下記バナーをクリックして「施術体験」のページをご確認ください

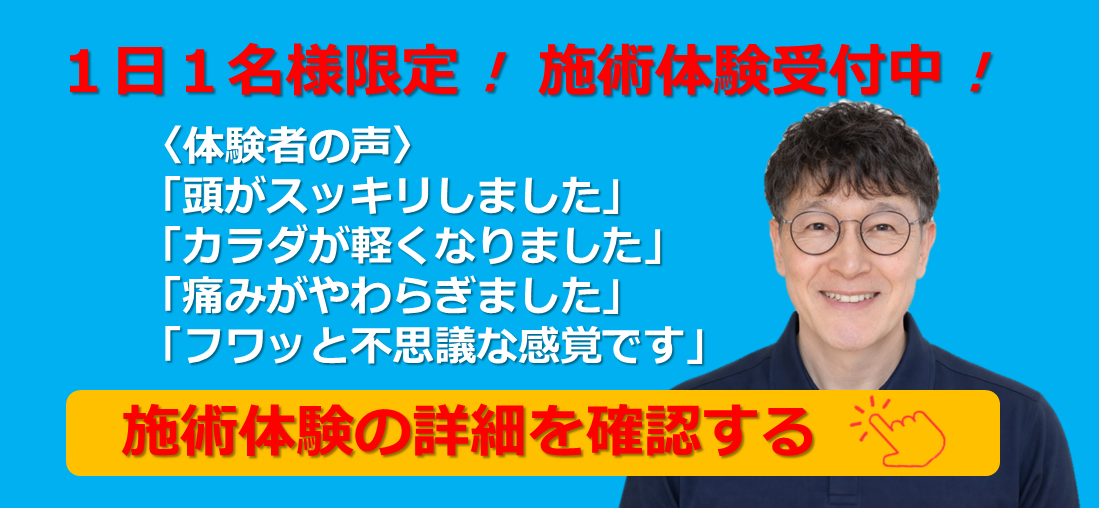
※既存の利用者様のセッション時間確保のため人数に制限を設けさせて頂いております



